「標的は11人」
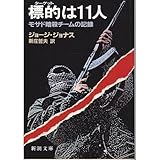
標的(ターゲット)は11人―モサド暗殺チームの記録 (新潮文庫)
- 作者: ジョージジョナス,新庄哲夫
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1986/07
- メディア: 文庫
- 購入: 1人 クリック: 20回
- この商品を含むブログ (58件) を見る
映画「ミュンヘン」原作。
スピルバーグが原作をどう脚色したのか興味があって読んでみました。でも映画を見て、「ここは創っただろう」、「ここは原作から変えただろう」とケチをつけたところはみんな原作そのままでした。
暗殺チームが総勢5人は少なすぎると思いましたが、これは原作は通り。1つのチームに11人全員を暗殺させる無茶な任務も原作通り。モサドから金銭面以外の支援を受けずに活動するのも原作通り。ギリシャのアジトでPLOの面子と一晩同宿する羽目になるのも原作通り。仕掛けた爆弾が爆発しないので仲間が勝手に突撃するのも原作通り。女殺し屋に仲間の1人が殺されて、オランダまで報復に出向く原作通り。ノンフィクションにしてはちょっと面白すぎます。
それに設定や細かいエピソードだけではなく、全体的なストーリーもどこか人工的です。
- 主人公の父はかつて英雄と呼ばれたが今は国に見捨てられ失意の人生を送っている。この父の存在は主人公にとっては半ば烙印となっている。これはよくある設定で、主人公の行く末と物語の結末を暗示している。
- 主人公は祖国を脅かす敵の討伐を命ぜられる。仲間は4人。総勢5人は特殊工作チームの人数としては少なすぎるが。これをパーティとして見るのなら5人は適正人数。主人公がノーマルタイプのファイターでリーダー役。他の仲間は一つ何かの特技があって、性格面でも一癖あるというのはお約束
- わずか5人で敵の強大な勢力に立ち向うのはもちろん無茶な話。この戦力差を埋めるためにファンタジー系でありがちな話では神々や妖精族が主人公に力を貸すというテコ入れがなされる。「標的は11人」で妖精さんの役を演じるのはル・グループとよばれる国際的犯罪組織だ。組織のボスはパリ郊外に居を構える農園主。どこか精霊の長を思わせるような人物でパパと呼ばれている。
- こうして妖精の力を借りた主人公達は敵のボスキャラを次々と倒していく。最初のこそ慎重に行動するが、経験を積んでいくうちに大胆になるが、やがて敵の影に脅えるようになり、仲間は1人又1人と傷つき倒れ、主人公も果てしのない戦いに倦み疲れていく。
- それでも苦闘の末に偉業を成し遂げ祖国に凱旋する。だが広い世界を見慣れた主人公にとって故郷は狭く感じられ、人々の心も偏狭に過ぎた。祖国のために戦った人間が故郷喪失者になってしまうという皮肉な結末。
巻末の「著者あとがき」および「取材ノート」によると、1984年に原作が出版された当初、内容の信憑性を巡って大きな議論が巻き起こったそうです。世界中のマスコミがあら探しをしたが、細部に至るまで疑わしい点は見つからなかったと著者は「取材ノート」に誇らしげに書いています。
しかしこの本、ど真ん中に書いてあるのは典型的な英雄伝説です。肖像画に例えると背景や人物の周囲にさり気なく置かれた静物は正確に描かれているのに、着ている服は実物よりもずっと立派で、まして頭についているのはギリシャ彫刻かた引っ張ってきたような英雄の顔。そんな感じです。
果たしてこれはノンフィクションと言えるのでしょうか?